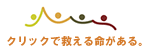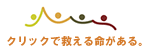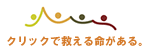プロスペクトパークでFemi Kutiのフリーコンサートへ行く途中のこと。
ソーホーのオフィスから地下鉄へ乗ろうとした矢先に、次々と携帯にメッセージが入り込んできたのだ。
「Is MJ really dead?」「Michael Jackson died!」「R.I.P Michael Jackson」
初めはデマだと思ったけど(そう思いたかった)、次々に来るのでこれは本当かもしれないと思い始めてきた。
コンサートが終わって、レストランで友人たちとご飯を食べていたら、CNNでマイケルの死にまつわるニュースが報道されていた。
デショーンは、マイケル・ジャクソンの大ファンだ。
音楽ヲタクとも言える彼が、一番大好きなミュージシャンとして尊敬してやまないマイケルの死はかなりの衝撃を与えたらしく、
コンサート会場で会った友達たちとも、マイケルの死についての話題について彼は固く口を閉ざしていた。
その彼が、CNNを見て、急に泣き始めた。
彼の涙を見て、ああ、本当にマイケルは死んでしまったのだと私ははじめて実感した。
一緒に夕食をともにしていた友人たちも、デショーンの涙を見て、みんな無言になった。
昔、今は亡き祖母が好きなレコードを買ってくれるといい、私は「マイケル・ジャクソンのレコードがいい!」とお願いした。妹は確か松田聖子だったと思う。
私はマイケルが大好きだった。彼に夢中になっていたといってもいい。
多分、アイドルの感覚で彼に憧れていたのだ。
自分が成長するにともない、今度は彼の音楽のすごさに尊敬の念が生まれた。
彼は国境も人種も言葉も文化も超えて、世界が一つになることをいつも望んでいた。
そして、未来は子供たちにあると夢を託した。
そういうことを、自らの命を削って一生懸命表現していたはずだ。
彼がこの世を去った日、確かに何かが一つになったような気がした。
その日、私たちは家に着いて、マイケルの歌を2人で再び聴いた。
デショーンがいてもたってもいられなくなり、ソファーから立ち上がって私の手をとった。
そして狭い部屋で、マイケルの歌に合わせて2人で馬鹿みたいに踊った。
踊って踊って、汗をかくほど踊って、最後に「Got to be there」が流れ、また2人で涙を流した。
私はマイケル・ジャクソンに会ったことはない。
コンサートも見たこともない。
こんなふざけたファンの一人にも、彼の存在はしっかりと大きく刻み込まれている。
マイケルのことを書こうと思ったら、もうきりがない。
今日の追悼式でスティーヴィー・ーワンダーが「神が彼を必要とした」と言った。
マイケルは、この世の仕事を終えたのだ。
マイケル、ありがとう。本当にありがとう。