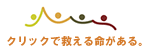彼はニューヨーク出身のパフォーマーで、世界中を公演旅行をしてまわっていた。
その人と私は東京で出会い、恋に落ちてしまった。
その頃私はまだ大学生で、進路のことでとても悩んでいた。
自分が何をしていいかわからなかったし、不安で、自信がまったくなかった。
そんな私と正反対に、その人は毎日のように、多くの観客から拍手喝采を浴び、きらきらと輝いているように見えた。
彼は、いつも自分が何をしたいのかが明確であり、自信に満ちあふれていた。
しかし、時々何かのインタビューに答える彼は、今でこそ成功しているがここまで来る道は決して平坦ではなかったと語るのだ。
今でも英語は得意ではないが、その頃の私はもっと苦手で、彼とのコミュニケーションを取るのも精一杯、しかも自信がないので、どうしてこの人は私と一緒にいるのか不思議で仕方なかった。
彼は、私をニューヨークに呼び、彼の家族まで紹介してくれ、また将来の話までし始めるのだ。
彼と将来を誓い、家族を築くことを考えたとき、私自身がどうしても釈然としなかった。
また、その当時、私の母は体が丈夫ではなかったため、海外へ出たいという強い思いはあっても、その母を置いて日本を出るという決断はとてもできなかったし、自分が何をしたいのかもわからないという、何か中途半端な状態で飛び出すことに、抵抗があった。
もしかしたら、その彼と一緒に世界を旅しながら、色々なことを吸収し、自分の道を開くことができたかもしれない。
しかし、彼の成功に乗って、“彼の彼女”というステイタスに安住し、自分もそこにいるような感覚が気持ちよくもあり、怖くもあった。
彼の友人たちーやはり第一線で活躍している人たちーに紹介され、一緒に時間を過ごすとき、一瞬自分もそこに”いる”ような錯覚に陥るが、実際はまったく宙ぶらりんで生温い自分という現実のギャップに、落ち込むのであった。実はまったくその位置にいないと自分が一番よく知っていたからだ。
彼は、自分の人生を「決めて」きたのだ。ずっと。そして、私は決断し、そのコミットメントが恐怖でもあった。
写真を撮ろうと決めたときと、彼との別れは同時期だった。
偽るという苦しみから逃れると同時に、今度は「向き合う」という恐怖と対面しなくてはならなかった。
ニューヨークにいる彼の元を去り、一度私は東京へ戻った。
私が彼のいるニューヨークへはもう戻らないと、彼はきっと、わかっていたと思う。
ちょうど1月の寒い頃であり、家族が寝静まっている明け方、彼の実家へ電話をした。
「もう、わたしたちは一緒にいられないね」
「そうだね。わかってる」
本当に短い会話だったが、他に話すこともなかったので、そのまま私は受話器を置いた。
解き放たれた思いと一緒に、涙があとからどんどん溢れてきた。